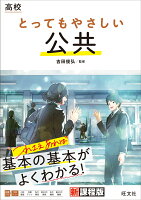大学受験、共通テストに臨み、「公民」はどの科目を選択すべきか、悩んでいませんか?この記事では、各科目を選択するメリットや注意点など、入試科目の選択について必要な考え方や、時間を節約しながらできる具体的な勉強法も丁寧にレクチャーします。
また、すぐに使える問題集や参考書も紹介しますので、ぜひ最後まで読んで大学入試対策の参考にしてくださいね。
この記事は2018年12月に書かれた内容を一部最新の情報にリライトして投稿したものです。
1. 大学受験における「公民」選択の注意点
「公民」は「地理歴史」と並ぶ社会科の教科ですが、共通テストにおいては『公共,倫理』『公共,政治・経済』『地理総合/歴史総合/公共』の3科目で構成されています。注意点として、①『公共,倫理』『公共,政治・経済』の組み合わせ②同一名称を含む科目の組み合わせはできないと定められています。また、『地理総合/歴史総合/公共』は原則1科目しか受験できないため、特に2科目選択の文系受験生は避けるべきでしょう。
「地理歴史」を構成する科目と合わせて、これら「公民」科目を選択するかどうか、また、どの科目を選択するかを判断することになります。最も重要なのは、自分の志望する大学・学部ではどの科目が試験対象か、という点をしっかりおさえておくことです。
例えば、国立大学の文系学部では、共通テストにおいて「地理歴史」・「公民」から合わせて2科目の選択を必要とするケースが多いですが、早稲田大学文学部の個別試験では、公民を試験科目として課していません。
まずは、自分自身が目指す進路や受験する大学・学部をしっかり見定め、試験情報を確認した上で、どの科目を選ぶのか、対策用の学習を進めていくのか決定しましょう。
2. 共通テストでの科目選択について
2-1. どうやって選択科目を決める?
共通テストで科目を選択する場合は、つい過去の平均点を見て点数が取りやすい科目に目が行ってしまいがちですが、自分の志望大学においてどの科目が試験対象か、選択が可能かという点は何よりも重要です。
選択肢があるとすれば、その中で自分の興味がある科目や好きな科目を選ぶことをおすすめします。大学受験の対策は年単位で勉強を続けていかなければなりませんから、仮に点数が取りやすい科目だとしても、学習を進める間ずっと気が重いというのでは、受験勉強全体に影響してしまいます。
例えば、社会情勢にあまり興味が持てないという人にとって、「公共,政治・経済」などはやはり面白みのない暗記科目として負担になってしまうでしょう。
つまり、興味・関心を含めた自分の適性を見た上で、選択科目を総合的に決めることが大切と考えてください。
2-2. 「公共」とは
「公共」とは2025年度の新課程共通テストから新設された科目で、旧課程の「現代社会」を発展させたような内容となっています。文部科学省の学習指導要領においては、「公共」を通して「社会的事象等を、倫理、政治、法、経済などに関わる多様な視点(概念や理論など)に着目して捉え、よりよい社会の構築や人間としての在り方生き方についての自覚を深めることに向けて、課題解決のための選択・判断に資する概念や理論などと関連付ける」力を学んでほしい、と求めているようです。
新設された公民科目を選択する上で、「公共」は必修科目となっており、単独での受験は出来ません。公民選択の人が最も注視しなければならない科目と行っても良いでしょう。「公共」は「政治・経済分野」と「倫理分野」をかいつまんだ内容が含まれていますが、「金融」などの「公共」独自の内容も含まれています。
3. 公民の科目別おすすめ勉強法
3-1. 公共の戦略的勉強法
前述したとおり、「公共」は原則、「倫理」「政治・経済」とそれぞれ2科目1セットで実施されます。共通テストにおいては大問1と大問2が公共の共通問題となっており、『公共,倫理』『公共,政治・経済』どちらを選択するにしろ、同じ問題を解くことになります。積極的に参考書等での演習を行いましょう。新課程共通テストは2025年度から実施されており、まだまだ過去問は少ないですが、旧課程の『現代社会』『倫理』『政治・経済』『倫理、政治・経済』の問題も演習する上では有用です。問題傾向や内容が若干異なる部分はありますが、参考にすると良いでしょう。また、問題を解いた際に、分からない、回答に悩んだ、という箇所があった場合は、都度、資料集などで確認をおこないましょう。
なお、過去問を利用するにあたっては、大きな注意点があります。公共の勉強を進める際に大事なのは、学習対象の情報が古くては意味が無いということです。
政治や経済を取り巻く環境は年々変わっていますから、過去問が出題された段階で常識だった社会的動向が変わっていた場合、逆に誤った情報ということになってしまうおそれがあります。その点はしっかり注意しておきましょう。したがって、最新の教科書や資料を用いることがまず大事です。
3-2. 倫理の戦略的勉強法
思考力を問う共通テストといえども、一問一答のような「暗記で出来ていれば解ける」問題も出題されます。思想家の名前とその人の思想、あるいは歴史に残る言葉などを元にした問いが選択方式で出題されますので、まずは人名と思想が結びつくように覚えることが大切です。出題範囲も西洋思想から日本思想まで幅広くなっています。1つの分野を深めるというよりかはひとつひとつの知識は浅くてもよいので、はじめは軽く一周して内容をさらっておきましょう。公共と同じく、旧課程の共通テスト過去問も活用できるでしょう。
ただ、共通テストの傾向として会話文や資料を通して思想を読み取ったり考えたりしなければならない問題も多く出題されています。既存の知識を活用してもう一段階思考しなければならない問題もあるので、参考書を活用して問題に慣れておくことも大切です。
対策に有効な勉強法やおすすめ参考書・問題集については、こちらの記事にまとめています。
>>【新課程】共通テスト公民分野の2科目目はどうする?倫理で確実に点数を稼ぐための勉強法
3-3. 政治・経済の戦略的勉強法
社会科系科目の中でも特に暗記と演習が重要となります。まず時事問題の情報に目や耳を傾け、アンテナを張りましょう。メディアとして、テレビは時間の拘束が長く、CMを見せるための演出やバラエティ性が高いので、貴重な時間を無駄にしてしまうことが多いです。
ここでは、社会性が高いラジオ番組を聞くことをおすすめします。
特におすすめするのはTBSラジオの「荻上チキ・ Session」です。月曜日~金曜日の18時~21時まで放送している番組ですが、主要な内容はインターネットでいつでも聞くことができるサービスが提供されています。
ですからリアルタイムで聞く必要が無く、時間の制約もありませんし、住んでいる地方に関わりなくネット上で聞くことができるのでとても便利です。時事問題をいち早く扱うことが多く、情報源としても、問題の成り立ちをゼロから理解するための教材としても優秀です。
これらの方法で受験年度の10月頃までは大きな時間を使わず、他科目の勉強の合間にコツコツ知識や情報のインプットを重ねましょう。11月以降は記憶や理解を確かなものにするため過去問に取り組みましょう。
4. 公民の科目別おすすめ参考書
公民の科目は、大学受験対策の比重として、英語や数学などより優先順位が低くなりがちです。そのため、できる限り時間をかけずに効率よく勉強を進めたいものです。効率的な学習のための、おすすめ参考書を紹介します。
4-1. 現代社会のおすすめ参考書
『高校 とってもやさしい公共』(旺文社)
共通テストの公共を基礎の基礎から解説しており、独学でも始められる1冊となっています。重要項目が分かりやすくまとめられているので、効率よく勉強を進めることが出来るでしょう。社会に多く時間をかけられない、社会が苦手という人にもおすすめです。
4-2. 倫理のおすすめ参考書
『蔭山の共通テスト倫理 改訂版 』(学研教育出版)
有名な参考書で知っている人も多いと思いますが、講義形式の参考書で、所々にカラフルなイラストが挿入されているため、視覚的に要点をおさえていくことができます。全体の流れをとらえるには最適な参考書で、まず勉強の基礎となる枠をしっかり頭に入れることができます。
なお、読む時には黙読でなくキーワードを音読していくと、より効果的に学習することができるでしょう。
4-3. 政治・経済のおすすめ参考書
『畠山のスパっとわかる政治・経済爽快講義 [改訂第7版]』(Z会)
共通テストから二次対策まで幅広く行えるので、自分のレベルにあわせて利用できます。講義形式でポイントがまとめられており、実際に授業を受けているかのような臨場感の中で、知識の定着から理解まで行うことができます。入試問題や最新時事も掲載されているので、これ1冊で政治・経済はカバーできると言っても良いでしょう。
4-4. 共通テスト対策に向けてのおすすめ問題集
上記の参考書である程度知識をつけたら、問題演習に移りましょう。時間の許す限り、なるべく多くの問題にあたりましょう。おすすめは以下のシリーズです。
『共通テスト 公共、倫理 集中講義 改訂版』(旺文社)
『共通テスト 公共、政治・経済 集中講義 五訂版』(旺文社)
「公共、倫理」は過去13年、「公共、政治・経済」は過去10年分のセンター試験・共通テストを分析し、重要度を示しています。テーマごとの「基礎力チェック問題」で覚えた知識を確認・定着させることができ、「チャレンジテスト」は、共通テストの実戦演習として取り組むことができます。また、別冊で「一問一答問題集」が付属しているので、直前の見直しにも活用できる1冊です。
5. まとめ
大学受験における公民の立ち位置と学習の取り組み方、具体的な勉強法などをまとめました。
まず「現代社会」「倫理」「政治・経済」(政経)「倫理,政治・経済」(倫政経)の4つの科目の中で、希望する大学でどの科目で受験できるかなどを確認することが重要です。その上で、自分自身が興味を持てたり、得意と感じたりするかなどを合わせて考慮し、選択科目を判断することをおすすめします。
また、「公民」はセンター試験レベルであれば、極端に専門的な知識が求められることはありません。時間をかけずに最大限の成果を得るという勉強法に早い段階から徹していれば、恐れる必要はない科目ですので、効率よく対策に取り組みましょう。
共通テスト社会についてはこちらの記事も参考にしてください!
>>【新課程】共通テスト「地歴・公民」はどう変わる?科目選択における注意点と試験内容のポイント
>>【共通テスト】日本史の勉強法と攻略におすすめの参考書 ~問題形式別の対策で得点8割以上を目指す!~
>>【社会科目選択】大学受験で後悔しない選び方と各科目のおすすめポイントを現役大学生が解説!